こんにちは、yuuです。
今日は、古くからよく使われる四文字熟語「温故知新(おんこちしん)」についてご紹介します。昔の知識や経験を大切にしながら、新しい気づきを得るという考え方は、今の時代にも通じる普遍的な学びの姿勢です。
「温故知新」の意味
「温故知新」とは、昔のことを学び直して、そこから新しい知識や理解を得ることを意味します。
この言葉は『論語』の子罕篇に登場し、孔子が
故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る
と述べたのが由来です。つまり、過去を振り返ることで未来への道しるべが見えてくる、という教えです。
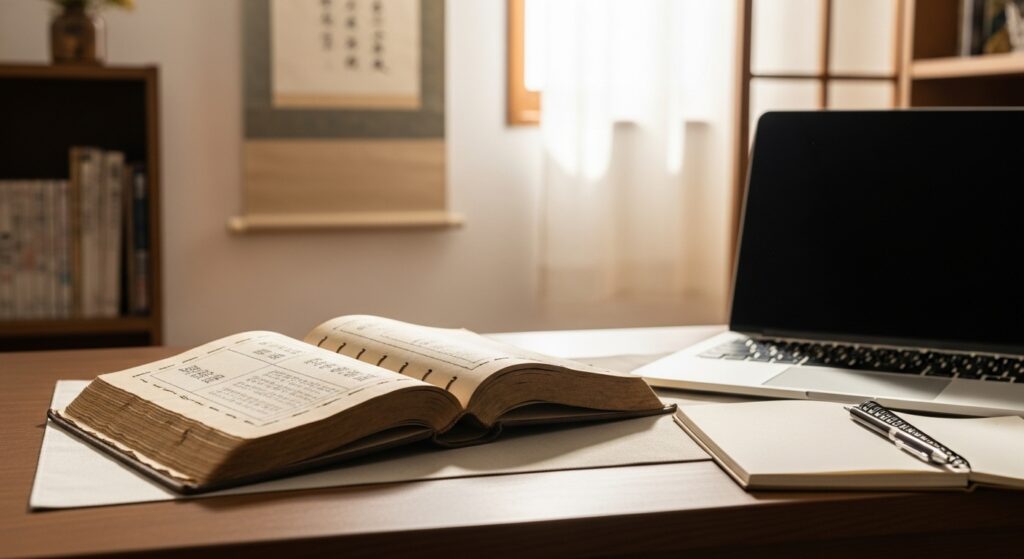
補足:「古」と「故」の違い
- 古(こ・ふるい)
「古いもの」「昔のこと」を表す漢字。
例:「古典」「古代」「古本」 - 故(こ・ゆえ・ふる)
本来は「理由・原因(ゆえ)」を意味しますが、古くから「昔の」「以前の」という意味でも使われます。
このため「故(ふる)き」と読んで「古いこと」と同じ意味で用いられることがあります。
例:「故郷(ふるさと)」=昔からの郷里、「故人(こじん)」=昔なじみの人
👉 つまり「温故知新」の「故」は「古」の略字ではなく、「故」自身が持つ『昔のこと』という意味を使っているのです。
補足:「温(たず)ねる」という読み方について
「温」は通常「あたたかい」と読みますが、漢文訓読では「温(たず)ねる」と読まれることがあります。
「温故知新」の場合は「古きをあたため直す=復習する」という意味で使われ、ここでは「たずねる」と訓読されます。
この「たずねる」は「訪ねる」「尋ねる」と同じ読みをあてていますが、意味としては「復習する」「学び直す」に近いものです。
👉 訓読特有の読み方であることを知っておくと、理解がぐっと深まります。
使い方と登場する場面
「温故知新」という言葉は、日常会話で頻繁に使うものではありませんが、節目やあらたまった場面で耳にすることが多いです。
- 学校の授業や受験勉強
国語の教科書や小論文の題材として登場し、「古典の代表的な言葉」として紹介されます。 - 会社や団体のあいさつ文
年頭所感や式典のスピーチで「これまでの歩みを温故知新し、新しい挑戦につなげていきたい」といった形で用いられます。 - 新聞や社説
歴史や文化を振り返る記事、あるいは社会の課題を論じる場面で「温故知新の姿勢が必要だ」と書かれることがあります。
👉 このように、「温故知新」は人生や社会を振り返りながら未来を考える文脈でよく使われる言葉です。
類義語・対義語
- 類義語:学而不厭(学びに飽きない姿勢)
- 対義語:付和雷同(他人に流される)、我田引水(自分の利益だけを考える)
→ 詳しくはこちら:四文字熟語「我田引水」とは?意味・由来・使い方をやさしく解説
「温故知新」は自分自身の学びに基づいて成長する姿勢を表し、他人に依存する姿勢とは対照的です。
現代に活かす「温故知新」
「温故知新」の考え方は、昔から変わらず大切にされてきました。
現代社会においても、その姿勢はさまざまな場面で活かすことができます。
- 歴史を振り返り、次の社会づくりに役立てる
- 過去の経験を見直し、新しい挑戦のヒントにする
- 伝統や文化を大切にしながら、新しい価値を創り出す
「温故知新」は、単なる知識の習得ではなく、未来を切り開くための姿勢そのものだと言えるでしょう。
まとめ
「温故知新」とは、過去を振り返り、そこから新しい学びを得ること。
私たちが日常で直面する課題や決断にも、この姿勢は大きなヒントを与えてくれます。
関連記事:
言葉の奥深さをもっと楽しみたい方へ。

昔の知恵から新しい遊びを見つけたら楽しいにゃっ







